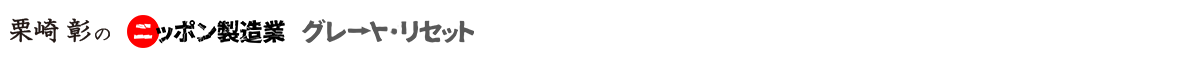第十章:「酸っぱいブドウ」と日本の製造業のデジタル化
2025年3月24日
|
日本の製造業にはグレート・リセットが必要です。 根本から変わらなければならないと思っています。 このコラムでは、日本の製造業にグレート・リセットが必要な理由を詳細に書いていきます。 日本製造業復権の主人公は、製造業に携わる皆さんです。 このコラムがそのための議論のきっかけを提供できれば、それ以上にうれしいことはありません。 栗崎 彰 |
目次

イソップ寓話の「酸っぱいブドウ」は、多くの人が知る教訓話である。
キツネが木の上にあるブドウを取ろうとするが、どうしても届かない。
仕方なく諦める際に、「どうせあのブドウは酸っぱくてまずいのだ」と負け惜しみを言う。
これは「手に入らないものを否定することで、自分を納得させる心理」の典型例とされる。
この寓話が示す心理は、私の知る日本の製造業の経営幹部がデジタル化に対して取る態度と驚くほど似ている。
彼らはデジタル化の重要性を理解している。
しかし、現場の反発や短期的な利益の減少を恐れ、改革に踏み切れずにいる。
その結果、「デジタル化は日本のものづくりには合わない」「我々の強みは職人技であり、デジタル化がそれを損なう」といった言い訳を繰り返す。
これは、まさに「酸っぱいブドウ」の心理そのものではないか。
デジタル化の重要性は理解しているが…

経営者がデジタル化に対しておびえ、慎重になるのには理由がある。
第一に、デジタル化は単なるツールの導入ではなく、業務プロセスそのものを変えることを意味する。
そのため、現場からの抵抗が必ず発生する。
長年の経験に基づく職人的な技術やノウハウが軽視されるのではないかという懸念も根強い。
第二に、短期的な利益への影響が避けられない点も大きい。
デジタル化には投資が必要であり、それがすぐに利益に結びつくとは限らない。
特に、伝統的な製造業においては、ROI(投資対効果)を短期間で求める傾向が強く、長期的な視点での投資を敬遠する風潮がある。
第三に、「うちの会社には合わない」という心理的なバイアスがある。
例えば、欧米の企業が積極的にデジタル化を進めていることを見ても、「あちらは大量生産が主流だが、我々は高品質の少量生産だから事情が違う」と理由をつけて導入を見送る。
これも、「どうせあのブドウは酸っぱいのだ」と決めつけるのと同じ論理である。
一方で、デジタル化を進めない言い訳を並べながら、会議では「グローバル競争に勝つ」と威勢のいい発言をする幹部も多い。
しかし、何の対策も打たずに勝てるわけがない。
まるで運動もせずに「オリンピックに出場する」と豪語するようなものだ。
成功している企業との差は広まるばかり
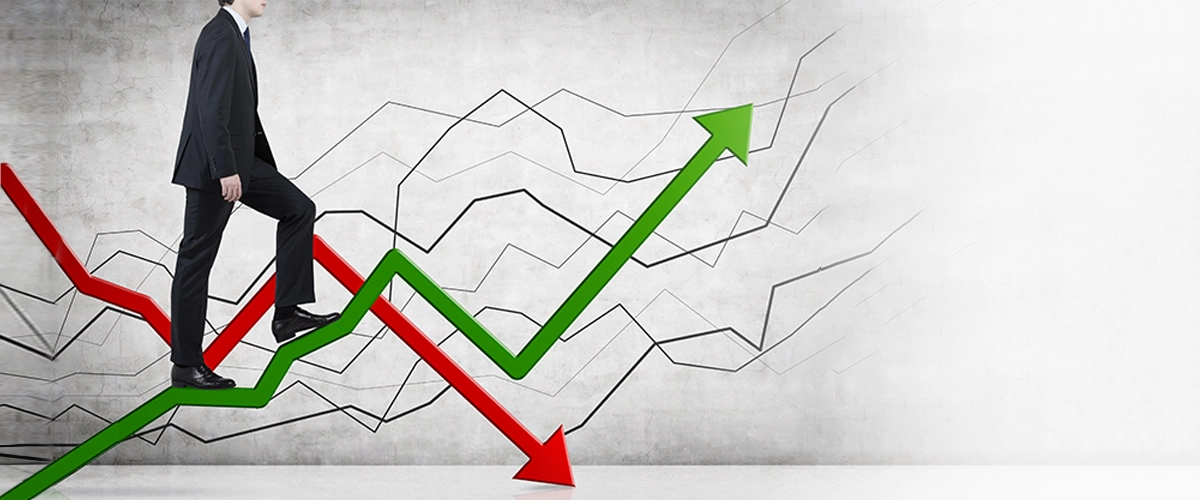 しかし、実際にデジタル化に取り組んだ企業は、確実に成果を上げている。
しかし、実際にデジタル化に取り組んだ企業は、確実に成果を上げている。
第一章でも触れたが、例えばある工作機械メーカーは、IoT技術を活用して機械の稼働状況をリアルタイムで把握するシステムを導入した。
その結果、ダウンタイムが削減され、歩留まりが向上した。
また、AIを活用した品質管理を導入した企業では、熟練工の技術をデータ化し、より安定した品質管理が実現している。
さらに、デジタルツイン(仮想空間上で製造プロセスをシミュレーションする技術)を導入することで、試作のコストや開発時間を削減した例もある。
欧米の先進企業では、すでにデジタルツインを活用した生産ラインの最適化が当たり前になりつつあり、日本企業がこの技術を避け続ける理由はどこにもない。
それにもかかわらず、日本の製造業の幹部たちは「今はタイミングではない」「社内の理解が得られない」「前例がない」と言い続ける。
前例がないからこそ先駆者になれるという発想が欠けているのは実に皮肉な話である。
手を伸ばさないなら、ブドウの味は分からないまま
 経営者は、ブドウを遠くから眺め、「どうせ酸っぱい」と言っているだけではないか。
経営者は、ブドウを遠くから眺め、「どうせ酸っぱい」と言っているだけではないか。
デジタル化を推進することによる短期的な困難を恐れ、結局何も変えないという選択をしていないか。
確かに、変革には痛みが伴う。
しかし、それを恐れて手をこまねいていては、競争力を失う一方である。
ブドウが本当に酸っぱいのか、それとも甘いのかは、実際に口に入れてみなければわからない。
キツネのように負け惜しみを言うのではなく、勇気を持って手を伸ばすべき時はすでに来ているのではないか。
デジタル化を避け続けることで、日本の製造業はゆっくりと衰退していく。
一方で、積極的に変革を進めた企業は、既に次のステージへと進んでいる。
デジタル化は避けられない潮流であり、「うちの会社には関係ない」という言い訳は、もはや通用しない。
今こそ、日本の製造業は「酸っぱいブドウ」から目をそらすのではなく、手を伸ばし、果実の甘さを確かめる時である。
それができるかどうかが、これからの日本の競争力を左右する鍵となる。
もし今後も「タイミングが悪い」と言い続けるつもりなら、世界の競争相手から見れば、日本の製造業はただの怠け者のキツネでしかない。
必要なのは、逆算による選択と集中戦略
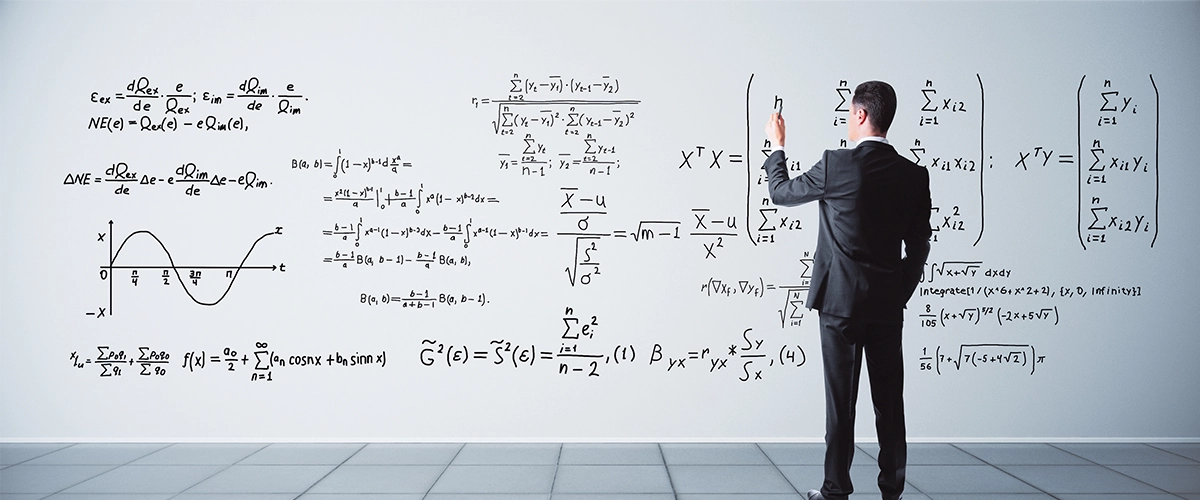 ブドウを手に入れる方法はいくつかある。
ブドウを手に入れる方法はいくつかある。
長い棒を持ってきてブドウを落とす。
木登りの得意なサルにお願いする。
他にも考えられるだろう。
ここでわかることは、ブドウを手に入れるためには、何らかの道具や他の生き物の協力が必要ということだ。
組織と道具立てである。
デジタル化というブドウを手に入れる方法は千差万別だ。
ツールは星の数ほど存在し、社内外も含めて協力を期待できる関連組織も多岐にわたる。
選択肢は大量にある。
どの選択肢がいいのか。
それには「逆算」が必要だ。
次回は、千差万別のデジタル化の技術導入のヒントにしていただけるような逆算の方法について解説する。
ちなみに先月、日経BP 総合研究所が編纂した「製造業DX調査レポート2025-2035」という技術レポートが発刊された。
「今こそ実効性のあるDX戦略を。この1冊で、次の一手を描く。」という謳い文句には、「日本の製造業のDX対応はこれからなのか。やはり周回遅れなのだな」と感じてしまった。
発売のプレスリリースを見ると、調査に協力した製造業393社のうち、「DXに前向きに取り組んでいる」と回答した企業は354社らしい。
さらに、この中で “「高度なデータ活用」によってDXを推進する意欲”について「非常に意識している」および「やや意識している」と回答した企業が全体の69.5%を占めたそうだ。
この数字は多いとみるべきか少ないとみるべきか。
そして、「前向きにDXに取り組んでいる」というその内容は気になる。
もし購入された方がいたら、ぜひ感想を教えていただきたい。