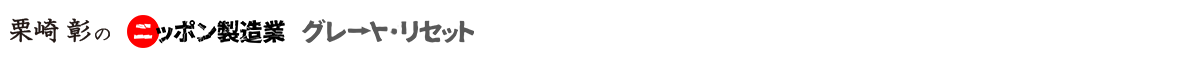第二章:Japan WAS No.1
|
日本の製造業にはグレート・リセットが必要です。 根本から変わらなければならないと思っています。 このコラムでは、日本の製造業にグレート・リセットが必要な理由を詳細に書いていきます。 日本製造業復権の主人公は、製造業に携わる皆さんです。 このコラムがそのための議論のきっかけを提供できれば、それ以上にうれしいことはありません。 栗崎 彰 |
Was No.1
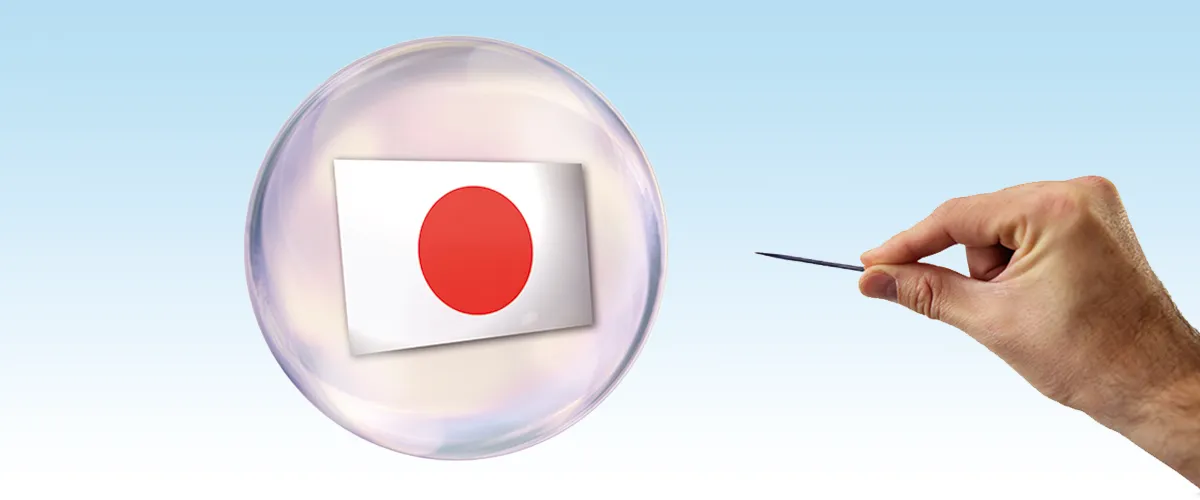
私と同世代の方なら、社会学者エズラ・ヴォーゲルによる1979年の著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という書籍が、日本でベストセラーとなったことを記憶しているだろう。
この本の原題は『Japan as Number One: Lessons for America』で、日本語に訳すと「世界のトップとしての日本:アメリカへの教訓」である。
日米貿易摩擦が激化していた当時、戦後の日本が高度成長を遂げた要因について社会や企業のありかたを分析し、学ぶべきことを紹介した内容だ。
発行されたのが、日本が高度成長期を迎えて自信を持ち始めた時期とも重なったせいか、タイトルを「Japan is No.1」、つまり「日本は世界のナンバーワン」と誤解した人が多かったのも、ベストセラーの要因の一つともいわれている。
さらに2000年代に入り、日本の競争力が衰えると、「Japan was No.1」と揶揄される言葉も聞かれるようになった。
「is No.1」当時と「was No.1」現在との比較
しかし、実際に「Japan is No.1」と呼ばれても遜色のない時代があったことも確かだ。その原動力となった製造業の勢いは、デジタル技術の民主化によって過去のものになりつつあるが、まず、バブルの絶頂期であった1989年の世界での日本の位置付けを見てみよう。
1989年 vs 2019年
左側の1989年当時のランキング50位の中に、日本企業は2/3を占める32社も入っている。
トップ10には大手インフラおよび金融機関が5社。 そして、製造業関連企業が11社。
この時代の日本の製造業を「No.1」と呼んで何の不足があるだろうか。
そして失われた30年を経た2019年。
右側の2019年当時のランキング50位の中に入っている日本企業は、トヨタ自動車一社のみである。
2024年現在は、トヨタ自動車の順位が変わっているだけで、状況に変わりはない。
世界時価総額ランキングだけが企業の現状や勢いを定義するものではないが、今となっては、日本の「No.1」は「as」でも「is」でもなく、過去形の「was」以外の何物でもない。
【出典】STARTUPS JOURNAL「平成最後の時価総額ランキング。日本と世界...その差を生んだ30年」
注1:平成31年の表はYahooファイナンスのデータ
注2:平成元年の表はダイヤモンド社のデータ
私は1981年に社会人となった。
社会人としての自覚が定着し、仕事にも慣れた1987年、バブル景気が始まった。
バブル崩壊は1991年。
日本の凋落の結果となった政治的要因や分析は、これまで散々され尽くしてきたし、その原因は複合的で無数の変数が絡んでくる。
私は学者でも知見者でもないので、論理を展開する文章は書けない。
しかし、製造業を支えるアプリケーション・エンジニアとして、バブル景気を経験した立場と視点から、二点に絞って「was」の理由を挙げてみる。
ハードウェア信仰と情報の価値に対する認識の甘さ

STARTUPS JOURNALが発表している2024年の企業の世界時価総額ランキングを見てみると、IT(Information Technology)、通信、サービスを担う企業が上位に目立っている。
どれも「情報」を扱う企業だ。
情報という商品が、インターネットという経済の道路を使って、高速に大量に流れる仕組みに関わることが、大きな利益をあげている。
私が若い頃は、ソフトウェアはハードウェアの付録的な位置付けであった。
IBMや富士通の数億円のメインフレーム・コンピューターを購入すれば、OSは、ハードウェアの一部として一緒に納入されることが当たり前だった。
その認識は、自然とソフトウェア軽視という文化を生んでしまったのではないだろうか。
現在のWindowsのように、OSを買うという認識のかけらもなかった。
性能のいいハードウェアを作りさえすれば、それこそがものづくりの真髄であると盲信してしまったのだろう。
どんなに素晴らしい包丁を作って新鮮な素材を用意しても、料理の達人がいなければ、美味しい料理はできない。
欧米の情報産業企業は、ソフトウェアとサービスに目をつけただけでなく、ハードウェアも込みでエコシステムを作った。
エコシステムとは、製品、サービス、コンテンツが連携して、大きな利益を生み出す仕組みだ。
ひとつの例をあげるとすればAppleが適当だ。
iPhoneという製品をコアとしてアプリを販売するApp Store、音楽を販売するiTunes Storeがある。
そしてiPhoneはiPad、MacBookなどAppleの他の製品とつながる。
それぞれが補完して大きな利益構造を構成する。
日本の情報産業は、欧米から大きく遅れをとっている。
その証拠に、日本には、FacebookやX、LINEのようなSNSのインフラとなる世界的なシステムはない。
日本は、「情報」の価値とエコシステムというコンセプトに気づくのが遅すぎた。
トップダウンで物事が進まないボトムアップ文化

私は米国と欧州の企業で働いた経験がある。
出張ではなく、そこで生活をしていた。
国民性、生活習慣、もちろん言葉・・・いろいろな違いに戸惑ってばかりだった。
米国企業と欧州の企業の間でも、もちろん違うことが多かったが、変わらないことがただひとつあった。
それは、組織の情報伝達の方向である。
スピーディな狩りを得意とするトップダウン型欧米企業
欧米では、その方向はトップダウンだ。
経営者が何かを決定すると、その結果は素早く下に降りてきて、一気に全社に浸透する。
この起源には、狩猟民族気質が関係しているような気がする。
何人かが動物を囲んで、それを仕留めるには、強力なリーダーシップを持つ人が必要だ。
動物の習性を把握し、仲間に司令を出し、時と場合によっては自らが囮となる。
トップダウンの頂点に立つべき人は、知識と行動力とそれに伴う覚悟を持っている。
私が書籍の共著をさせていただいた内田孝尚氏は、工学博士で日本機械学会のフェローを務める。
彼はホンダでCADとCAEを推進した責任者である。
その立場上、ホンダで採用したCADやCAEの開発元主催のユーザー会に出席するために何度か海外に出向いた。
そのユーザー会では、日本企業と欧米企業の出席者の違いに愕然としたそうだ。
BMW、Audi、その他欧米からの出席者はすべて役員クラスだった一方、日本の企業からは一担当者しか出席しなかったという。
他社の重鎮たちと直接情報交換ができる場に対する熱意の差はそれだけ大きい。
トップダウン型の欧米各社の役員は、政府主催の議会にまで出席し、産業育成政策に関わることもある。
そこで方針が策定され、トップダウンで各企業内に落とし込まれる。
部門長が方針の策定に従い施策を設定し、担当者がその施策に準じたツールを選定し、ルールを作り、マニュアルを作成し、全社に浸透させる。
知識と行動力とそれに伴う責任感で、対応がスピーディになる所以だ。
何事もみんなの同意が必要なボトムアップ型日本企業
日本は、村社会を生きる農耕民族気質と言われることが多い。もちろんリーダーシップを持つ人は必要であり、その役割が存在したであろう。
ただ狩猟民族のような爆発的な瞬発力よりも、皆で話し合い、何事も全員同意の上で進めることに重きを置いてきた。
民主的な方法ではあるが、責任を分担するということは、責任を持つ人がいないということでもある。
組織の情報伝達の方向も、ボトムアップ型と言える。
例えば、何か新しい施策を始める場合、担当者が現場に準じたツールを選定し、ルールやマニュアルを作る。
それを行うために、上長の説得が必要となる。
大抵の場合、上長は判断できず、その判断を経営層に持ち込んでも、経営層は理解できない。
経営層と担当者の間で、稟議のラリーが行われる。
このとき、何か新しい取り組みを浸透させるためには、特にラリーの往復回数は増える。
例えば「情報」などという形のないものの価値が高まっていた時代ですら従来の方法で対応していたならば、その結果、当然の遅れをとることになる。
トップダウン vs ボトムアップという構図で「情報伝達の速さ」は、間違いなくトップダウン型に軍配が上がる。
日本の製造業が世界市場から置き去りにされた理由の考察は、人によって立場によって異なる。
以上のふたつの理由は、筆者の40年の定点観測のみからの見解であることを付記しておく。
現在の製造業の産業構造の中で、ボトムアップ型はトップダウン型に勝てないのか。
次回は、その筆者なりにそのヒントを探っていきたい。
次の回「第三章:ボトムアップ型組織の逆襲」へ