Coffee Break vol.2: 皆さんからのお便りにお返事します
2024年12月27日
|
日本の製造業にはグレート・リセットが必要です。 根本から変わらなければならないと思っています。 このコラムでは、日本の製造業にグレート・リセットが必要な理由を詳細に書いていきます。 日本製造業復権の主人公は、製造業に携わる皆さんです。 このコラムがそのための議論のきっかけを提供できれば、それ以上にうれしいことはありません。 栗崎 彰 |
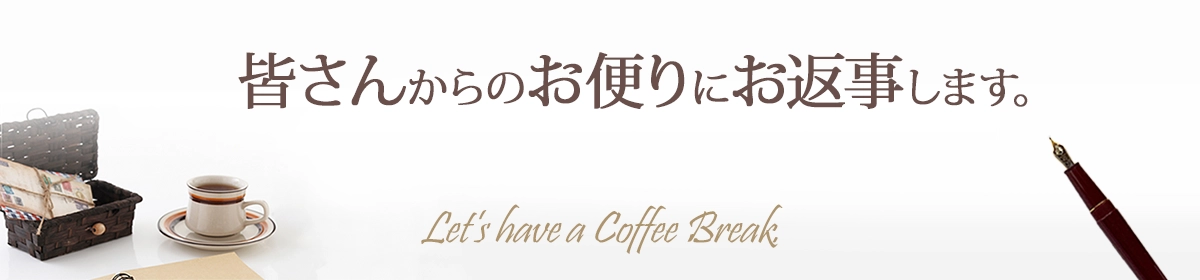
このコラムに感想をお寄せくださった皆さんのお便りを紹介するコーナー第二弾です。
先週、「ホンダと日産自動車が経営統合へ」という一大ニュースが世間に衝撃を与え、今でも様々なメディアで盛んに議論されています。
個人的には、驚きながらも「やはりそうなるか」という気持ちでもありました。
折しも先月、自動車関連企業のエンジニアの方々から、本コラムの感想をいただいたばかり。
このニュースが旬なうちにお返事をしたためたいと思います。
✉ その1 なんでもマンパワーで解決しようとする現場にいる人間は、どのように声を上げるべき?
✉ その2 上に立つ人間は技術の話が通じず、時間がかかるばかり。他社も同様?
✉ その1: なんでもマンパワーで解決しようとする現場にいる人間は、どのように声を上げるべき?
|
設計業務に関わる技術者として、おっしゃっていることがすごく当てはまり、現場はなぜにこんなにマンパワーで解決しようとするのだろうと思う部分ばかりだなと感じています。
改善点・問題点を上げても費用対効果はなどと言われ(必要なのは分かるけれど)、トップから変わろうという気概を感じないのが自動車業界ではないかと感じます。 業務効率/品質を上げるためのCAE活用について、トップから変わってもらうためには、ボトムであるわたくしたちのような人間はどのように声をあげたら伝わるのか、教えてほしいです。
(※原文を少し編集させていただいています)
|
設計の現場で活躍する設計者からのお便りです。
第六章を読まれてのご感想です。
マンパワーで解決しようとするのは、それしか方法がないからだと思います。
日本企業の現場力は世界一、それが日本の製造業の真髄だ、ということは事実で、それが日本の国力を押し上げてきました。
問題は、世界がものすごい勢いで変わって行くことを無視したことです。
見て見ぬふりをしたのか、興味がなかったのか…。
「現場力」という飴玉をほおばって味わっているうちに、世界は変わってしまったのです。
欧米では、十数年前からデジタル技術やバーチャル・エンジニアリングを積極的に導入し、いろいろな問題と対峙しながら新しい設計製造技術を構築してきました。
その国々の政府は、積極的にものづくりに関わる外郭団体を多数作り、支援しました。
まさに国家的プロジェクトとして製造業を後押ししたのです。
製品も設計も複雑化する一方で、働き方改革という名のもとに設計時間は削られていきます。
現場力は「匠の技」の成れの果てです。
匠の技は神格化され、そこに改善点や問題点は存在してはいけないのです。
もし改善点や問題点を進言したとしても、その効果を測るのは短期的な金勘定だけです。
このような状況を打破できるのは、行政と教育です。
さて、「トップから変わろうという気概を感じないのが自動車業界」という厳しい意見をいただきました。
その答えは出始めています。
ホンダと日産の経営統合が発表されました。
数年前は考えてもみなかったことです。
社風も車風もまったく異なるふたつの会社が本当に統合できるのか。
テレビのコメンテーターは無責任な持論を展開していますが、「そんなことは言っていられない危機的な状況」の末の結果です。
今回の経営統合は、経営者の敗北です。
IT技術の理解と投資を怠ってきたツケがまわってきたのです。
イーロン・マスク氏のような、世界を見渡す視野と技術力を持つ者しか、会社を引っ張っていくことができないのです。
「業務効率/品質を上げるためのCAE活用について、トップから変わってもらうためにはボトムからどのように声をあげたら伝わるのか」ということについては、即答できる答えはありません。
私自身、四十数年、その活動をしてきましたが、夢叶わず、です。
もちろんいくつかの成功事例はあります。
小さな会社ほど、CAEやその他のIT技術の導入はスムーズです。
部署間の壁や忖度や駆け引きがないからです。
会社が大きくなるに従って、改革の成功率は低くなります。
匠の技をコアにした現場力をぶっ壊して、設計や製造のワークフローを再構築することが手っ取り早いやり方ですが、それは事実上、できないことです。
それでも、CAEの活用については上層部も納得しており、推進している企業がほとんどです。
今できることは、不具合を起こした既存の製品や流用設計の改造ポイントについてCAEを適用し、その効果をカネに換算することです。
切り口は、工数、試作回数、実験回数など。
CAEの効果の証拠をたくさん作ることです。
その上で、「こんなに効果が出ているのに、どうして全社展開しないのですか? どうして標準プロセス化しないのですか?」という提言をしてみるのはいかがでしょうか?
それを阻止する上司がいたり、提言を具現化しない経営層であれば、それは公益通報を無視していることです。
お声がけいただければ、いつでもお手伝いします。
CAE活用のものづくりは私のライフワークですから。
✉ その2: 上に立つ人間は技術の話が通じず、時間がかかるばかり。他社も同様?
|
栗崎さんの仰る通り、欧米はかなりすすんでいる印象かつ、国内企業はボトムアップ型ゆえの弊害をかなり実感しています。
私の会社では技術者の役職者は少なく、上に立つ人間はマネジメント側の人間が多いです。いくらいい提案や内容の展開をしても話が通じず、時間がかかるばかりか、なぜか担当者の負担が増すばかり。いわゆる言ったもん負け、やったもん負けの文化が根付いているとも思えるような雰囲気すら感じます。 おそらくこういった状況に置かれる日本の企業は多いのではないかと推測します。 少しでも状況を変えるため、このコラムはチームのメンバーへ展開し、議論のきっかけとさせて頂きたいと思います。
(※原文を少し編集させていただいています)
|
「欧米はかなりすすんでいる印象かつ、国内企業はボトムアップ型ゆえの弊害を実感」されているとのこと。
ご自身で情報を収集し、それを実感として受け止めていることは、それだけで素晴らしいことだと思います。
日々の仕事に追われ、国外の情報どころか国内の情報収集さえおぼつかない人がほとんどだと思います。
だからこそ、経営層や中間管理職の方々の情報収集力と、それに根差した戦略を練ることが大切です。
どのような資質を持つ人が組織の上に立つべきか。
会社の昇進制度にはいろいろとあると思います。
私の知る範囲では、上に立つ人間は営業畑のマネジメント側の人が多いです。
これには日本の雇用形態が根強く残っているからです。
終身雇用制度は長い間、日本企業で当たり前の雇用方法として定着してきました。
しかし、現在は終身雇用制度に対する考え方は変わりつつあります。
日本の経済が低迷し、経営層はやっと重い腰を上げました。
海外ではデジタル化が進み、さまざまな作業がITの技術によって代替され、企業に求められるスキルの変化が激しくなってきました。
それに対応するためには、成果主義の雇用形態を取らざるを得ません。
とはいえ、成果主義の徹底にはほど遠く、専門知識がないから判断ができない、よって現場担当者に丸投げ…という図式が現在なのだと思います。
いくらいい提案をしても、判断ができないうえに責任を分担しようとするから、その調整に時間がかかります。
そのために必要なデータや資料も、すべて担当者が準備しなければなりません。
たち消えになってしまうかもしれないプロジェクトに、担当者は振り回されることになるのです。
しかし、現場に出ている私の肌感覚では、中間管理職もITや技術がわかる方々が増えてきているように感じます。
やがてその方達が経営層になるでしょう。
日本が生き残っていくためには、そのような変化が不可欠です。
ただ時間はかかります。
それを少しでも加速するために、その人達を後押しする切り口での活動を考えてみてはいかがでしょう。
皆さんのお眼鏡に叶う先見性を持った上司はいるはずです。
その人に情報を提供し、議論を重ね、小さくてもいいから突破口を作るのです。
大きなダムも小さな穴や亀裂から決壊します。
他にも多くのご感想・ご意見・ご質問をいただいており、製造業に従事する皆さんの現状やお気持ちを垣間見ることができる、大変貴重な場となっています。
時間の許す限り、お返事していければと考えておりますので、ぜひお気軽に感想フォームからご意見いただけますと幸いです。
それでは、良いお年をお迎えください。
来年こそ、日本の製造業が、少しでも盛り返すことを祈って・・・
次の回「第八章 : 3D設計のもたらす製造業ビジネス変革と日本の状況:~内田孝尚氏との対談<中編>~」へ
<栗崎 彰 著書紹介>
|
製造業においてデジタル化が普及する中、日本ではシミュレーションツールであるCAEの活用が遅々として進まない。世界の常識であるCAEを「ツール」ではなく「企業戦略」として活用すべき時が来た。 |
|
|
|
|
※読者プレゼントは終了しました。たくさんのご応募、ありがとうございました。
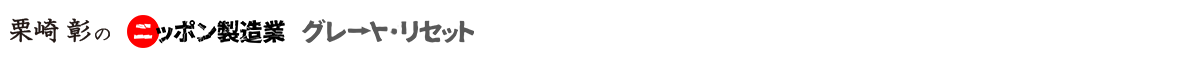
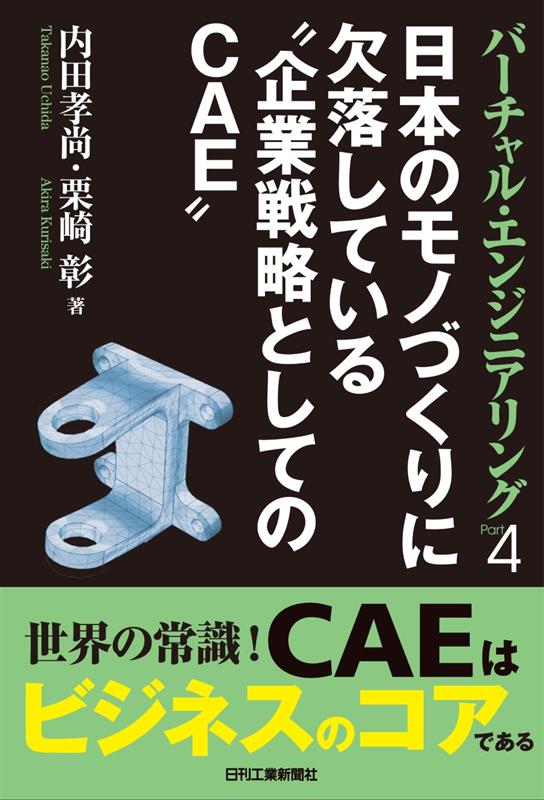 バーチャル・エンジニアリング Part4
バーチャル・エンジニアリング Part4 図解 設計技術者のための有限要素法 ~はじめの一歩~
図解 設計技術者のための有限要素法 ~はじめの一歩~ 図解 設計技術者のための有限要素法 ~実践編~
図解 設計技術者のための有限要素法 ~実践編~ 